9月29日(月)、TCU Shibuya PXU(東京都市大学渋谷パクス)にて、公開講座「原子力が拓く日本の宇宙開発」を開催しました。
開会に際して、はじめに本学の高木直行教授より趣旨説明があり、本公開講座では日本原子力学会「宇宙原子力技術」研究専門委員会による2年間の活動成果を報告するとともに、様々な分野からの参加者との意見交換を通じて、宇宙開発における原子力技術の応用の在り方について議論を深めていきたいとの話がありました。続いて、同 西山潤准教授より宇宙原子力技術研究専門委員会の設立経緯及び目的について説明があり、合わせて、本公開講座が宇宙・原子力分野へ携わる人材を増やす契機となるものとしたいとの抱負が述べられました。

基調講演では、本学の津村耕司准教授より、半永久的な電源・熱源である原子力電池(RTG)は今後の宇宙開発の鍵を握るデバイスであり、月面からの天文観測や外惑星探査を実現する上での大きな貢献を期待しているとの話がありました。

委員会報告では、はじめに宇宙航空研究開発機構(JAXA)の川﨑治氏より、宇宙用原子力技術を巡る日本や主要国の動向について、政策・技術開発の観点から紹介がありました。続いて原子力規制庁の岩永宏平氏より、原子力技術を宇宙開発に適用する場合の技術要件や課題について放射性同位体電池・熱源や原子炉などを事例として説明がありました。

「日本の宇宙開発に原子力はどう貢献できるか」をテーマとしたフリーディスカッションでは、はじめに以下の4名より、宇宙探査や技術開発、関連する政策動向や組織体制などの観点から話題提供がなされました。
・インターステラテクノロジズ株式会社 石津陽平氏
・株式会社東芝 木村礼氏
・日本原子力研究開発機構 菅原隆徳氏
・株式会社三菱総合研究所 川合康太氏
その後、津村准教授を加えた5名のパネリストと参加者によるディスカッションが活発に行われ、原子力に関する規制の中での技術開発の将来的な在り方や開発資金の獲得に向けた協業の方策などについて意見を交換しました。


閉会に際し、宇宙航空研究開発機構の船木一幸氏から、原子炉に関する技術開発について、経済的な観点からも議論を深めていくことが肝要であるとのコメントがありました。続いて、日本原子力研究開発機構の国枝賢氏から、月面原子炉や原子力電池の開発に若い人々が関わっていくこと、異分野融合や海外との連携が進展していくことを期待するとのコメントがありました。また、専門委員会を代表して高木教授より、原子力技術には、宇宙開発・探査の更なる展開を推進していく可能性があり、また宇宙開発への原子力技術の応用は若者を惹きつける魅力的な分野であることから、今後の大きな発展が望まれるとの話がありました。
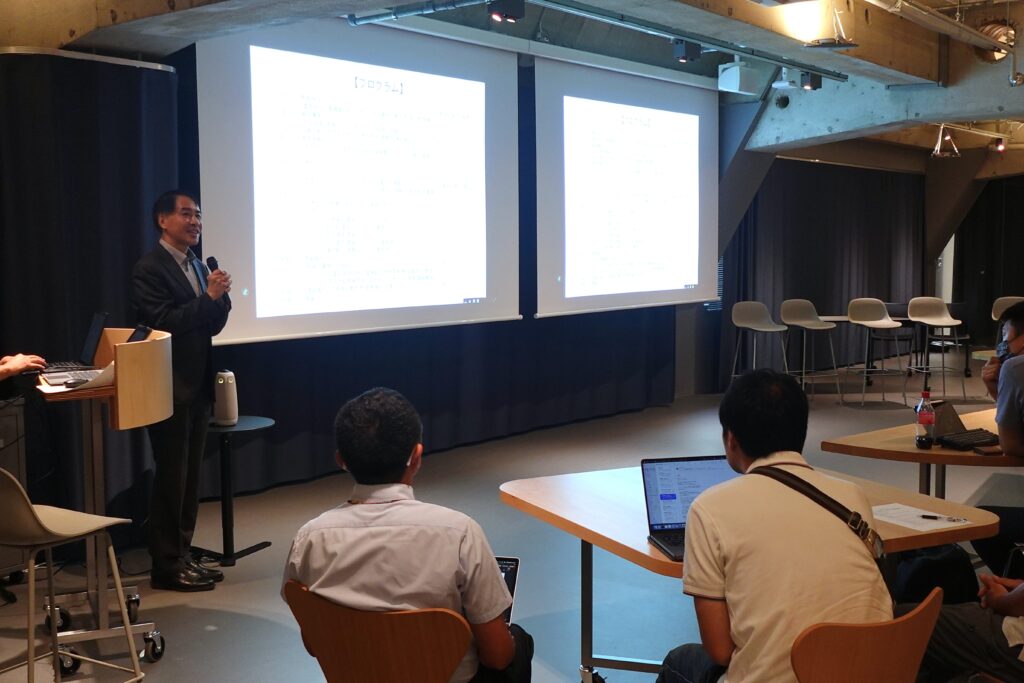
TCU Shibuya PXUでは、今後も新たな知見や交流の場を提供するイベントを企画してまいります。今後の展開にご期待ください。

