
11月7日(金)、TCU Shibuya PXU(東京都市大学渋谷パクス)にて、SXトラック第2回セッション「住み続けられるまちづくり(ライフスタイル/地域づくり編) ~好循環を生み出す地域のエコシステム共創戦略~」を開催しました。
はじめに、本学学長補佐の佐藤真久教授より開催挨拶があり、SXトラックでは「人間の成長」、「人間の生存」「社会の成長」「社会の存続」の視点から住み続けられるまちづくりについて議論を深めていくことを構想しており、本セッションでは好循環を生み出す地域のエコシステム共創戦略をテーマに、多様な主体が連携し、お互いに生き、生かされる地域の生態系(エコシステム)を構築するための方策を探っていきたいとの話がありました。
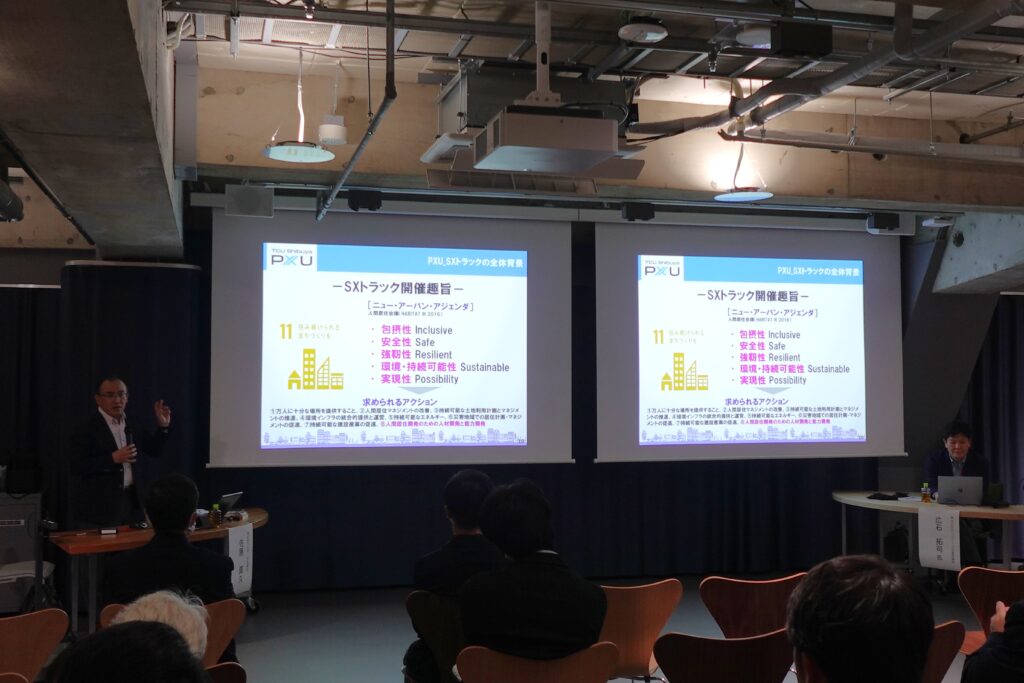
続く話題提供では、はじめに株式会社エンパブリック代表取締役/ソーシャル・プロジェクト・プロデューサーの広石拓司 氏より、「『社会にいいこと』から『社会を良くする』への地域のエコシステム共創戦略」とのテーマで話がありました。その中で、持続可能な社会へ変容していくためには、地域の文脈と関係性をベースとした実践や共創が重要であるとの提言があり、地域での生活を持続可能なものとしていくためには、地域文化や関係性、意思決定の在り方を変えていくことを目指すことが肝要であるとのコメントがありました。
続いて、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 執行役員/事業統括本部長の瀬田元吾 氏より「Jリーグクラブの地域循環共生圏創り」とのテーマで話があり、Jリーグが展開してきたSDGsに関する様々な取り組みや、特に水戸ホーリーホックが実施してきた地域との共生に向けた活動や社会・地域課題に解決を目的としたグリーントランスフォーメーション(GX)プロジェクトに関する情報提供がありました。
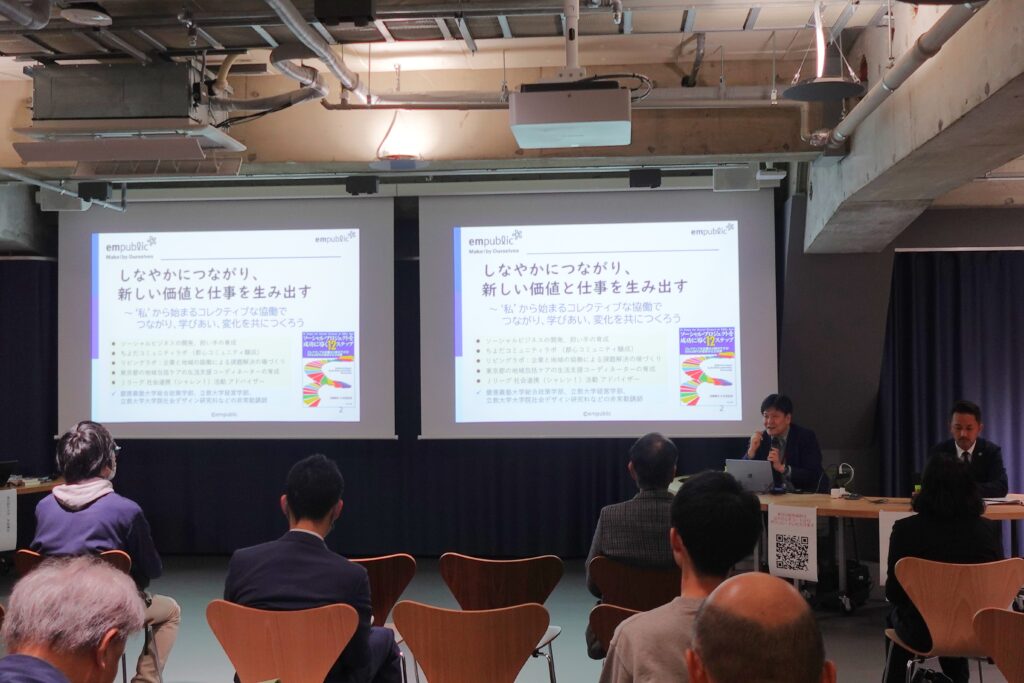

広石 氏・瀬田 氏の話題提供を受けて、参加者同士は自身が感じたことなどについて意見交換を行いました。また、司会の川邉雄司 准教授や会場の参加者から寄せられたコメントや質問を受けて、広石 氏からは、多くの人々と実際に出会うことを通じて地域やまちのことを知ることが重要であり、体験を伴う活動が変化を生み出す原動力となっていくのではないかとの話がありました。瀬田 氏からは、ゲーミフィケーションの視点を取り入れつつ、子供たちがSDGsを楽しく学ぶことのできるコンテンツを提供していくことがサッカークラブの果たす役割の一つであり、このヴィジョンを社会と共有していきたいとのコメントがありました。

クロージングでは、佐藤 教授や広石 氏、瀬田 氏から、住み続けられるまちづくりにおいて重要な点として、自分自身が主体的に関わりコミュニケーションを重ねていくことや、関係者にとって共通のアイデンティティとなり得るものをつくっていくことが挙げられました。

プログラム終了後に実施したネットワーキングでは、参加者同士が交流を深めるとともに、地域のエコシステム共創戦略について意見交換しました。
TCU Shibuya PXUでは、今後も新たな知見や交流の場を提供するイベントを企画してまいります。今後の展開にご期待ください。

