10月20日(月)、TCU Shibuya PXU(東京都市大学渋谷パクス)にて、一般社団法人グリーンCPS協議会と共催し、シンポジウム「混沌の時代における叡智と共創によるビジネス・組織・社会デザインへのアプローチ」を開催しました。

開会に際して、一般社団法人グリーンCPS協議会理事長で東京都市大学教授の中村 昌弘氏より、挨拶がありました。一般社団法人グリーンCPS協議会のこれまでの活動と、国内外の連携の広がりについて紹介されたほか、シンポジウムのテーマに基づき、非連続的な未来を創造する重要性について述べられました。
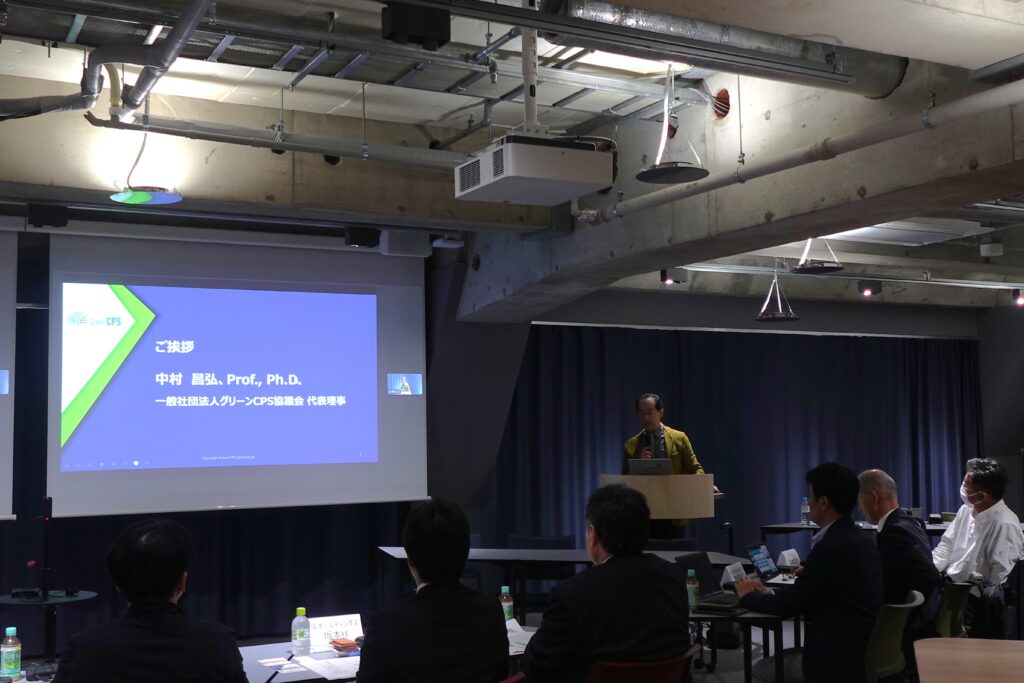
続いて、東京都市大学の野城 智也学長より、「木造建築の継手仕口から」と題した基調講演がありました。
日本の木造建築における継手・仕口技術を切り口に、暗黙知の継承とデジタル技術の進化について述べられました。建築分野における技術革新や情報共有の課題が紹介され、特にRobust TechnologyとFragile Technologyの概念の解説を通じて、技術の安定性と継承の重要性が示されました。また、BIM(Building Information Modeling)などの最新技術に触れつつ、建築における多様な視点の統合が今後の課題であると締めくくられました。

続いて、「暗黙のナレッジを形式知化するCollective Wisdom構想と普及活動~ポスト生成AI時代へ向け、集合知の形成を通じてヒトの存在価値を再定義する~」をテーマとしたセッション1では、以下の4名が登壇しました。
・一般社団法人グリーンCPS協議会理事長・東京都市大学教授 中村 昌弘 氏
・東京大学 梅田 靖 教授
・法政大学 福田 好朗 名誉教授
・早稲田大学 髙田 祥三 名誉教授
講演とパネルディスカッションで構成された本セッションでは、一般社団法人グリーンCPS協議会が、日本のものづくりの強みである現場の暗黙知を形式知化し、非専門家でも、専門家の知識を活用して一定の成果を出せるようにする仕組みづくりに取り組んでいることが紹介されました。また、暗黙知を体系化し、未来の競争力に繋げる可能性について、意見交換が行われました。

続いて、「産学 異種の対話と共創から生み出すイノベーション」をテーマとしたセッション2では、以下の5名が登壇しました。
・東京都市大学 大久保 寛基 教授
・東京都市大学 鶴田 靖人 特別教授
・株式会社グーフ 岡本 幸憲 代表取締役・エバンジェリスタ
・ビジネスシステムサービス株式会社 志村 健二 社長
・KPMGコンサルティング株式会社 黒木 真人 パートナー
本セッションでは、産学連携によるイノベーションの創出や、リカレント教育を含む人材育成の方法が取り上げられました。社会人と大学の交流拠点であるTCU Shibuya PXUのビジョンとして、渋谷をイノベーションディストリクトにする構想が示されました。また、印刷業界における人材育成の課題が紹介され、産学連携による教育の必要性が提示されました。学生の自由な発想と企業の知見を融合させる取り組みとして、インターンシップの事例も紹介されました。
さらに、産学連携による実践的な教育の可能性が示され、学生が産業構造やビジネスモデルを理解するための教育や、社会人のリカレント教育による組織変革の重要性が強調されました。インターンシップや企業との連携が、人材育成の鍵であることが語られました。
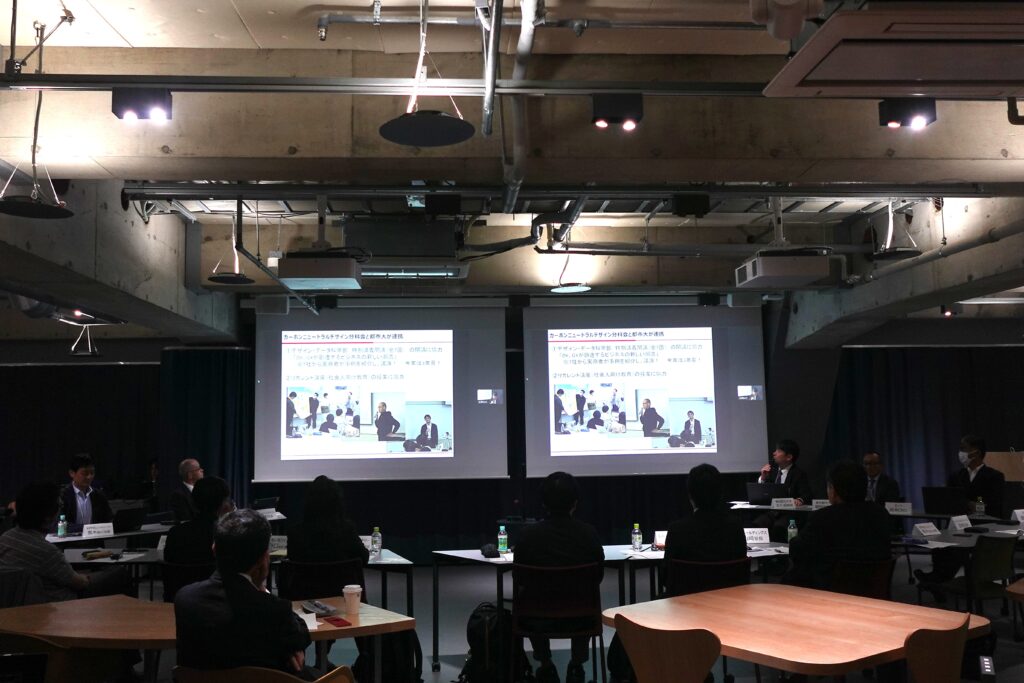
「GX/DX人材育成が加速する業務革新と価値創造、共創による地域・グローバル展開」と題したセッション3では、以下の5名が登壇しました。
・一般社団法人グリーンCPS協議会 近藤 真人 氏
・早稲田大学 伊坪 徳宏 教授
・株式会社兎ッ兎ワイナリー 野口 涼 氏
・宝ホールディングス株式会社 山﨑 耕太 氏
・石川県商工労働部 出雲 守 氏
また、以下の2名はビデオメッセージでの参加となりました。
・タマサート大学 Dr. Chawalit Jeenanunta
・ASTRAtech Mr. Henri Paul
本セッションは、企業、地方自治体、ASEAN諸国などを巻き込んだ人材育成と脱炭素活動を中心に展開されました。
企業や地方自治体によるサスティナビリティ推進や、DX/GX人材育成のための活動に関して、鳥取県のワイナリーの持続可能なワイン生産や、ASEAN諸国における脱炭素活動など複数の事例が紹介されました。最後に、企業内展開、企業間連携、地方行政施策をベースとした地域展開、そしてASEANを中心としたグローバル展開に向けた提言が示され、共創による価値創造の可能性についてまとめられました。

シンポジウム終了後に実施したネットワーキングセッションでは、参加者同士が活発に意見交換を行いました。
TCU Shibuya PXUでは、今後も新たな知見や交流の場を提供するイベントを企画してまいります。今後の展開にご期待ください。

